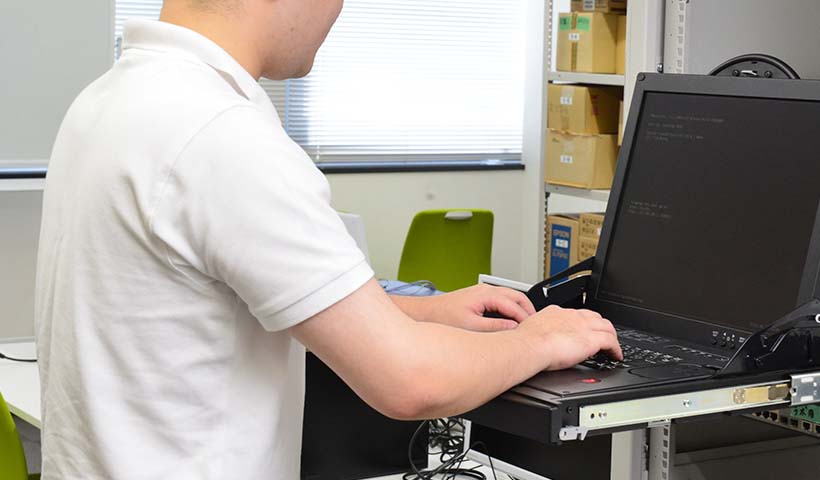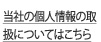システムエンジニア(パッケージシステム)


仕事の全体像
KIPの提供するパッケージシステムでは、市役所などの地方自治体、大学などの公共性の高い領域に展開しています。当社のシステム開発は96%が自社での開発案件のため、開発の上流工程(企画~提案)から下流工程(運用)まで一貫して携わることができます。
お客様との連携はもちろん、チームで協働していくことも非常に重要です。ひとりでは行き詰ってしまうことも協働することで、様々なアイデアからシナジーが生まれプロジェクトが加速します。
開発の全体の流れを以下のフロー図でご紹介します。

-
1 企画・提案
営業職が中心となって顧客先に提案するケースや、システムエンジニアと営業職が連携をして顧客に新しい機能を提案するケースがあります。
-
2 要件定義(分析)
お客様の要望を、どのようにシステムに組み込んでいくか、どの機能に影響があるかなどを事前に調査をするステップです。
求められている機能を実現するための解決策を明らかにします。 -
3 設計
要件を外部設計書と内部設計書に落とし込んでいきます。具体的には、次のステップであるテスト環境でもどういうテストが必要か明らかにするために、文字に起こすステップです。
-
4 開発・テスト
設計書を元にソースコードを書いていきます。テスト環境でテストをして運用への最終確認をします。
-
5 運用
導入後はシステムの使い方など、お客様からの問い合わせに対応します。その他にも、自治体業務では1年に1回実施をするような業務では、現場へ赴き、処理サポートを行います。バージョンアップ等を実施するケースもあります。
公共向けシステムの特徴
公共向けシステムの直接顧客は、自治体の職員様となります。私たちが提供するパッケージシステムによって自治体の業務が効率化することで、窓口の待ち時間削減や円滑な運営に寄与します。開発視点では、法改正による対応も必要となり、法律の知識も開発スキルと併せて蓄積していきます。
文教向けシステムの特徴
文教(大学)向けシステムでは、出願システムと教務システムを開発しています。大学職員様をはじめとして、受験生や学生などもシステムの利用者です。自社システムを開発しているため、お客様のご要望をダイレクトに反映でき、また感謝の声なども直接頂くことができますので、製品のこの部分の開発に携わっているんだとやりがいを感じられることができます。